
ドライバーの働き方改革によって起こる2024年問題
物流業界における「2024年問題」とは、働き方改革法案の規制内容が、2024年から物流業界にも適用されるために起こるとされる問題のことです。
2024年問題の原因として挙げられるのが、働き方改革の一環として労働基準法に規定された「時間外労働の上限規制」です。
近年、EC市場の急拡大により荷物の取扱量が急増する一方、トラックドライバーの若手不足や高齢化などが深刻化しています。
こうした状況下で、現役のドライバーは長時間労働が常態化しており、労働環境の改善が急がれる状況でした。
そこで打ち出されたのが、働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制です。
一般労働者に関しては2019年4月から(中小企業は2020年4月から)すでに上限規制が適用されています。
一方、トラックドライバーを含む自動車運転業、建設業、医師、鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業については、業務特性などから適用に5年間の猶予が設けられていました。
この猶予期間が終了し、ドライバーに対する上限規制の適用がスタートするタイミングが2024年だったのです。
2024年4月から適用された上限規制の内容
トラックドライバーの上限規制では、年間の時間外労働の上限が年960時間に設定されます。
規制適用後の年間・月間の拘束時間、ならびに1日の休息時間は次のとおりです。
| 以前 | 2024年4月以降 | |
|---|---|---|
| 年間拘束時間 | 実質3,516時間 | 原則3,300時間 (最大3,400時間) |
| 月間拘束時間 | 原則293時間 (最大320時間) |
原則284時間 (最大310時間) |
| 1日の休息時間 | 継続8時間 | 継続11時間を基本として 9時間を下回らないよう設定 |
上記のとおり、ドライバー1人あたりの労働時間が短くなるため、今後、労働力のさらなる不足が見込まれています。
2030年には輸送力が34%も不足する?
トラックドライバーの上限規制適用によって生じる影響について、経済産業省の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」は、輸送能力の不足を指摘しています。
同検討会の資料によると、コロナ禍前の2019年度の貨物輸送量などと比較した場合、2024年度には14.2%の輸送能力が不足し、2030年度には不足割合が34.1%にも上ると試算しています。
もし、試算どおりに約3割の輸送能力が不足する事態となれば、各産業や消費市場に大きな影響が出るでしょう。
食品物流が抱える3つの特有の課題

あらゆる産業の根幹を担っている物流ですが、中でも、食品物流は2024年物流問題の影響を受けやすいと考えられます。
なぜなら、食品物流は次に挙げる3つの特有の課題を抱えているからです。
課題1:手で行う作業が多い
食品物流は、衛生面への配慮が必要なこと、荷物サイズが小さかったり不均一だったりすることなどから、トラックの積み下ろしに際して手作業が基本です。
物流団体連合会ユニットロードシステム検討小委員会が行ったアンケート調査によれば、手作業での積み下ろしの多い品目の第2位に「青果物・米」、第3位に「加工食品(飲料除く)」がランクインしており、食品の積み下ろしの非効率性が明らかになっています。
特に農水産品の積み下ろしにかかる時間は平均3時間2分と、全品目の平均2時間47分に対して長いのが実情です。積み下ろしの手間が増えれば、当然ドライバーの負担が増えるほか、拘束時間も伸びてしまうでしょう。
課題2:長距離輸送が多い
食品物流の2つ目の課題として、主産地と消費地の距離が長いため、長距離輸送が多くなってしまうことが挙げられます。
例えば、魚介類や野菜類の一大産地である高知から、東京都中央卸売市場までの距離は約800km、トラックで輸送しようとすれば12時間を要します。
同様に、九州各地から輸送しようとすれば1,000km以上の長距離輸送となり、15時間以上の時間がかかってしまうのです。
食品物流はトラックによる輸送が全体の97%を占めており、トラックドライバーの長時間労働の要因ともなっています。
こうしたことから、物流業者による輸送費の引き上げや、取り扱いを断られるケースなども出てきている状況です。
課題3:輸送トラックの拘束時間が長い
前の2点とも関連しますが、輸送トラックの拘束時間の長さも食品物流の課題とされています。
食品物流は、消費ニーズや売上状況などによって出荷量が直前に調整されることが多いほか、市場や物流センターにおける荷下ろしの時間帯が集中する傾向にあります。
その結果、出荷元や物流拠点、配達先での待ち時間が長くなり、拘束時間が増えてしまうのです。
厚生労働省が行った実態調査によると、飲料・食料品の輸送では、拘束時間が「3,300時間以上」のドライバーが、2020年度から2021年度にかけて合計10%近く増加しています。
産業全体では拘束時間が減少傾向にある中、食品物流は今もなお拘束時間が長いままです。
ここまで紹介した3つの課題を解消していくことが、2024年問題を乗り越えるための重要なポイントになるでしょう。
2024年物流問題に対処しないと起こり得るリスク
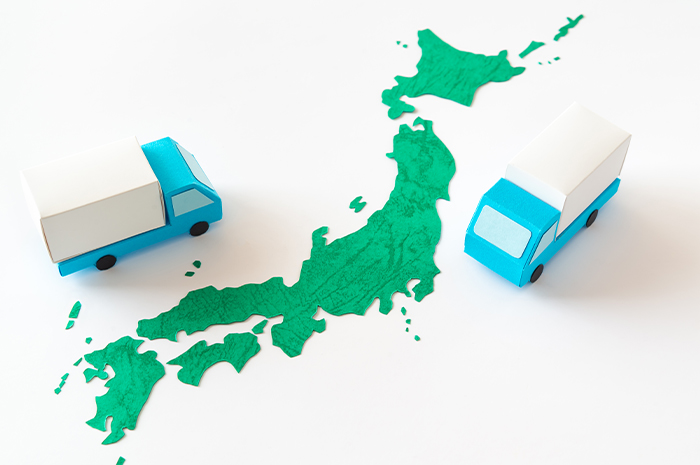
2024年物流問題は、食品物流にどのような影響を与えるのでしょうか。
今後起こり得る3つのリスクについて解説します。
輸送費高騰で価格転嫁せざるを得なくなる
ドライバーの働き方改革によって、1人あたりの労働時間が短くなれば、働き手がますます不足することが考えられます。
物流各社はドライバーを確保するために賃金をアップせざるを得ず、その分の費用が輸送費に上乗せされるでしょう。
小売店としては物流に頼らなければ営業ができないため、輸送費の値上がり分を商品価格に転嫁せざるを得なくなります。
輸送費の値上げによって利益率が圧迫されたり、商品の値上げで集客が減ったりすることがあれば、売上に影響が出る可能性があります。
長距離の食品輸送が難しくなる
働き方改革によって、ドライバーの休息時間もより長く設定されています。
これにより、長時間連続で運転しなければならない長距離輸送が難しくなる可能性があります。
先述のとおり、食品物流は、農産品を中心として生産地から消費地までの距離が長いのが特徴です。
仮にトラックでの長距離輸送が難しくなれば、仕入れ先の変更、中継地点となる物流拠点の整備など、物流体制の見直しが必要になるかもしれません。
従来の配送スケジュールを見直さざるを得なくなる
ドライバーの拘束時間を短くするため、荷主側でも、荷待ち時間を短くしたり、配送時間をピークタイムからずらしたりするといった対策が求められます。
とりわけ食品物流は荷待ちにかかる時間が長いため、対策の重要性は高いといえるでしょう。
また、稼働できるドライバーが減ることにより、物流業者が急な依頼に対応できなくなるおそれもあります。
上記より、これまでの柔軟でスピーディな配送が難しくなり、配送スケジュールの見直しが必要になる可能性もあるでしょう。
2024年物流問題に有効な3つの対策

ここまで2024年物流問題で起こり得るリスクを紹介してきましたが、対策を事前に講じておけば課題は解決できます。
食品スーパーや食品専門店向けの有効な対策を3つご紹介しましょう。
パレタイズで積み下ろしにかかる時間を削減する
食品の積み下ろしで手作業が多い理由として、バラ積み・バラ下ろしの多さが挙げられます。
ドライバーが箱を1個ずつ積み下ろししなければならないため、荷役時間が増えてしまい、拘束時間の増加につながります。
そこで検討したいのが「パレタイズ」です。
荷崩れしないように固定した荷物をパレットの上に載せるパレタイズにより、フォークリフトを使った作業が可能となり、ドライバーの手作業による負担を大幅に削減できます。
スペースを効率的に使えるようになるため、トラック1台の輸送量や倉庫に収納できる荷物の量も増えて、大きなコスト削減効果が期待できるでしょう。
パレットの規格化で物流効率をさらに向上
国土交通省は、パレタイズに関してパレットの統一規格を定めています。
規格は1.1m四方・厚さ14.4〜15cm・最大積載量1tです。
現状は業界や扱う商品によってパレットサイズが異なり、せっかくパレタイズを進めても、運搬するにあたって別のパレットに移し替える例も少なくありません。
これだとドライバーの業務効率が思うほど上がらず、パレタイズの効果が薄まってしまいます。
規格を統一することで、荷物の運搬効率向上やスペースの有効活用が進み、物流の課題解決につながると期待されています。
DX化により受発注や検品業務を効率化する
物流に関する業務のDX化を進めるのも、2024年物流問題への対策として有効です。
例えば、受発注業務をデジタル化して物流業者に共有しておけば、紙の伝票管理にかかっていた時間を削減できるうえ、伝票の紛失を防ぐこともできます。
アナログで起こりがちな受発注の伝達ミスも少なくなり、正確で効率的なやりとりが可能になるでしょう。
さらに、受発注システムと検品業務を連携して自動化すれば、検品がスムーズになり、ドライバーの待ち時間短縮が期待できます。
ほかにも、荷下ろし場の混雑状況をデジタル化して情報共有する仕組みを導入しておけば、情報を受けたドライバーは、混雑時に配送順を入れ替えることができ、業務効率の改善につながります。
物流のノウハウが豊富な企業に相談する
自社だけでは物流に関する課題を解決できないケースも多いのではないでしょうか。
そのような場合、物流のノウハウや経験が豊富な企業に相談するのがおすすめです。
信頼できる企業に物流関連を委託することで、業務の効率化や物流に関するコスト削減が図れます。
また、設備に関すること、売場に関することなど、関連する分野に関しても相談できれば、物流以外の分野でも効率化を実現できるでしょう。
包装資材の物流のことなら折兼にご相談ください

折兼グループは協力会社も含め100拠点以上の強力な物流網により、全国物流をトータルでサポートしています。
全国に広がる延床面積6万㎡もの自社倉庫スペースを活用することで、必要な商品を必要なだけご提供する「ジャストインタイム物流」を実現可能です。
もちろん物流に関するDX化にも対応。
オリジナルのWeb発注システム「o-pid」を使えば、受発注業務・検品業務を効率化できます。
初期費用・利用料をかけずに利用できるうえ、既存のシステムと併用することもできるので、すでにWeb発注を導入済みの企業でも活用いただけます。
ぜひ折兼までご相談ください。
物流業務の効率化で魅力的な店舗を目指しましょう
トラックドライバーの働き方改革を発端とする「2024年物流問題」は、物流全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。
物流においては、輸送費の高騰や長距離輸送の減少などが想定され、その影響は決して小さくありません。
しかし、トラックドライバーの労働環境が改善されることは、物流に関わるすべての業界にとってプラスに働くことも事実です。
これを機に物流に関する業務を効率化し、浮いた時間や人員を顧客サービスに向けることで、より魅力的で選ばれる店舗を目指すのがよいでしょう。






